建築業界に憧れて、「将来は設計や監理の仕事をしたい!」と考えている方も多いのではないでしょうか。でも、ひと口に“設計・監理”といっても、その道のりや働き方にはさまざまな選択肢があります。
今回は、建築の設計・監理を目指す人に向けて、進むべきルートや資格、働き方のスタイルなどを徹底解説します!
建築設計・監理の仕事とは何か、基本的な役割や違い
設計・監理を目指すうえでの主な就職ルート(6パターン)
ゼネコンとディベロッパーの違いと、それぞれの特徴
一級建築士の取得までの流れ(受験資格と登録要件)
自分に合った進路の考え方と選び方のヒント
設計・監理ってそもそも何?
- 設計:建物の図面を描き、構造・設備・意匠を計画する仕事。建築主の要望を形にする、まさに“建築の核”となる仕事です。
- 監理:工事現場において、設計図通りに施工されているかをチェックする仕事。施工管理とは異なり、“設計者の視点”から品質を見守ります。
この2つは切っても切れない関係で、設計だけでなく監理までできることが理想的。では、そのためにはどんな道があるのでしょうか?
 キキ
キキ実は、設計と監理を別部署や別会社で分けているケースも多いんです。とくに大手企業やハウスメーカーでは役割分担が明確で、設計担当が現場に行かないことも。でも、設計者としての力を高めたいなら、現場(監理)を知ることはとても大切。できれば、最初は両方経験できる環境を選ぶと◎
設計・監理を目指す進路はこの6つ!
① 建築設計事務所に就職する
小規模なアトリエ系から大規模な組織設計事務所まで、設計の中心で働くルートです。
- メリット: 設計の深い経験が積める/作品性の高い建築に関われる
- デメリット: 激務・低賃金のことも/現場経験は少なめなことも



“建築が好き”という気持ちをとことん突き詰められる環境。苦労も多いけど、設計スキルを真剣に磨きたい人にはうってつけです。
② ゼネコン(総合建設会社)に入る
施工を中核とする会社で、施工図作成や設計協力、監理業務を担当します。設計部門を持つ会社も。
- メリット: 現場の知識が深まる/監理力がつく/安定した待遇
- デメリット: 設計よりマネジメント寄りになることも



図面がどうやって実物になるか”を体感できるのがゼネコン。設計者としての“現場感”を持つと、後々のキャリアにも武器になります!
③ ディベロッパーに入る
土地の取得から企画・設計・販売までを行う“開発の起点”となる会社。
- メリット: 都市・街全体を見据えた設計視点/事業スケールが大きい
- デメリット: 設計自体は外部に依頼することが多い/ビジネス感覚が必要



“建築をつくる”というより“建築を生み出す仕組みを動かす”仕事。設計とは少し違うけど、都市や空間づくりに関わりたい人にはおすすめです。
④ ハウスメーカーに就職する(住宅+非住宅)
戸建住宅だけでなく、保育園・高齢者施設・店舗など、近年は多用途に対応する会社も多数。
- メリット: 安定した環境/設計の実務経験が積みやすい/BIM・CADが整備
- デメリット: プランがある程度定型化されていることも



“住宅しかやれない”と思っていませんか?最近のハウスメーカーは保育園や福祉施設も手がける多角化路線。実務を通して成長したい人にぴったりの環境です。
⑤ 公務員(建築技術職)になる
行政の建築職員として、審査・計画・公共建築設計などに関わるルート。改修の設計と監理なら行政で行う場合もあります。自治体によって、異なりますので、事前に確認を!
- メリット: 安定性/まちづくり全体に関われる/定時に帰れる環境も多い
- デメリット: 設計そのものに触れる機会は少なめ



民間では経験できない“行政の視点”から建築に関われる貴重な仕事。設計者とやり取りする側になりたい人、まちづくりに興味ある人におすすめ!
⑥ 独立・フリーランスとして働く
設計事務所を立ち上げたり、個人設計者として仕事を請け負う道です。実務経験・人脈・実績がカギ。
- メリット: 自由度が高く、自分の建築を実現できる
- デメリット: 経営・営業・収入の不安定さと向き合う必要あり



自由と責任はセット。若いうちに独立する人も増えてるけど、まずは事務所や企業でしっかり経験を積んでからの方が成功しやすいですよ。
資格はどうすればいい?
設計・監理において、一級建築士はほぼ必須といえる国家資格です。設計図の作成はもちろん、監理業務を正式に行うためには登録済の建築士である必要があります。
一級建築士を目指すステップ
- 建築系の大学・専門学校を卒業
→ これで「受験資格」が得られます(一部短大・専門卒は実務経験も必要) - 一級建築士試験を受験
→ 学科(筆記)と製図(設計製図試験)をクリア! - 登録要件:実務経験2年以上
→ 試験に合格しても、登録には「実務経験2年以上」が必要です。
また、建築設備士や構造設計一級建築士などの専門資格もあります。将来の進路に応じて取得を検討しましょう。



試験合格=ゴールではありません。“登録して初めて一級建築士”なので、実務経験も忘れずに計画しておきましょう!
自分に合った道を選ぶには?
設計・監理の世界は奥が深く、それぞれに魅力があります。どの道を選んでも、「自分は何を建てたいのか」「どんな建築を実現したいのか」を問い続けることが大切です。
✅ じっくりと設計を学びたい → アトリエ事務所
✅ スケールの大きい建築を手がけたい → 組織事務所やゼネコン
✅ 独立して自由な建築をしたい → 起業 or フリーランス



最初の一歩が“未来の全て”じゃないから安心して。途中で方向転換してもOK。まずは、自分が“どんな建築をつくりたいか”を考えるところから始めましょう!
最後に
設計・監理を目指す道は、一つではありません。
設計事務所、ゼネコン、ディベロッパー、ハウスメーカー、公務員、そして独立――それぞれに特性があり、学べることや向いている人も違います。
大切なのは、「どんな建築に関わりたいか」「どんな働き方をしたいか」という自分の想いを明確にすること。最初の選択で迷っても大丈夫。経験を重ねながら、少しずつ方向を調整していけばいいのです。
建築は人の暮らしに寄り添い、社会を支える仕事です。
あなたらしい一歩を、自分のペースで踏み出してみてください。
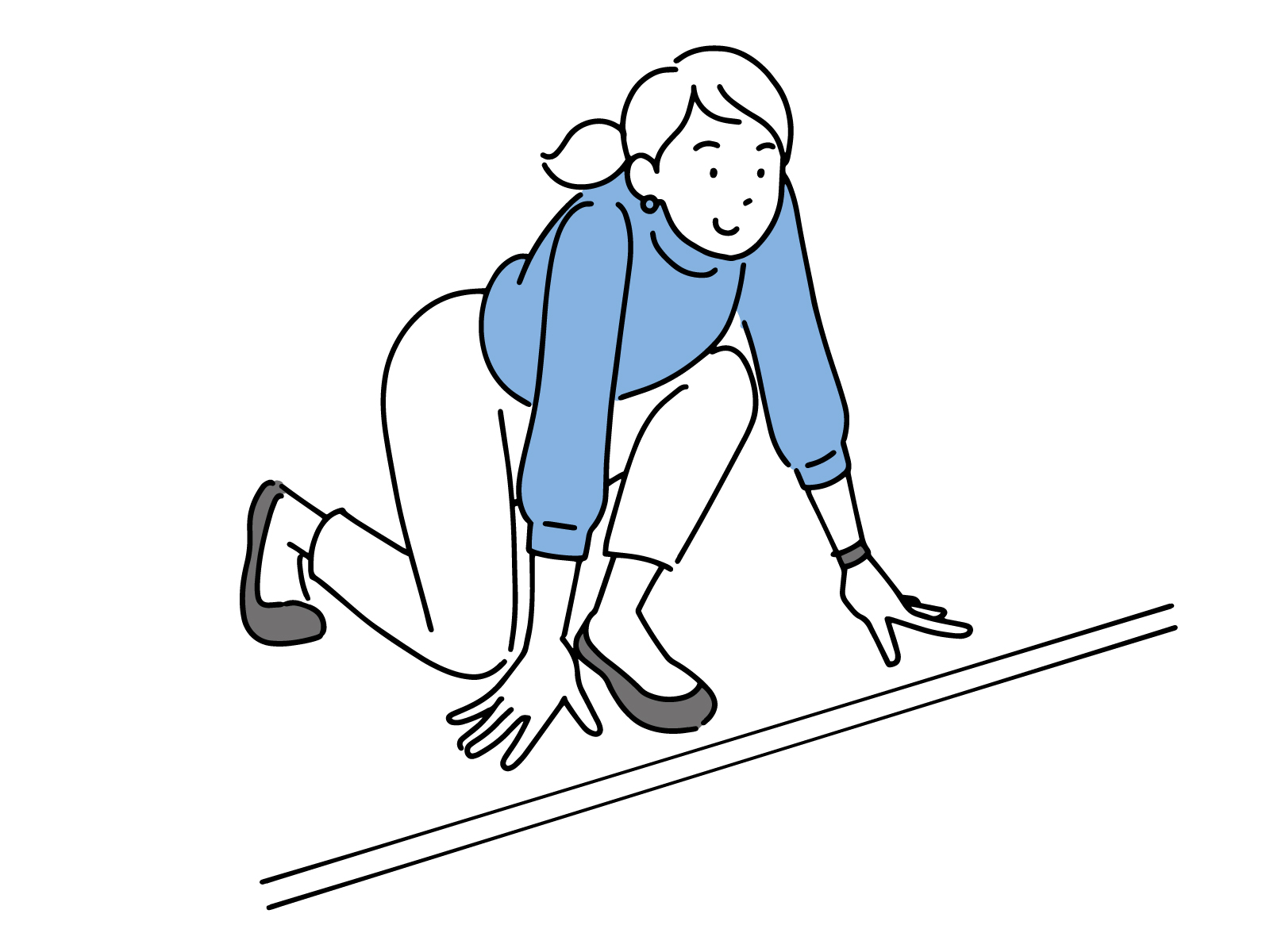









コメント